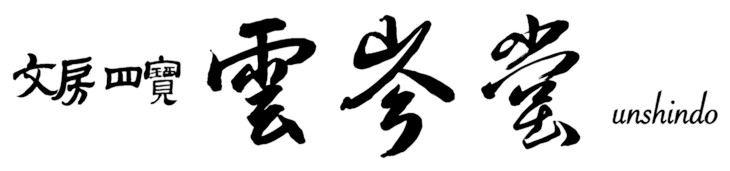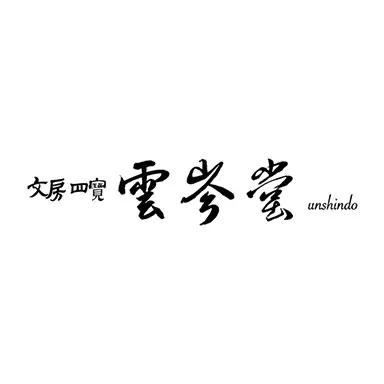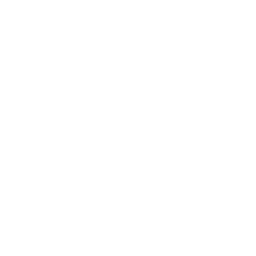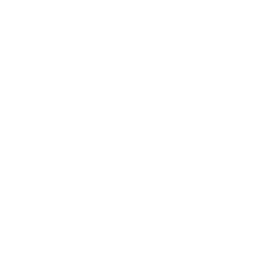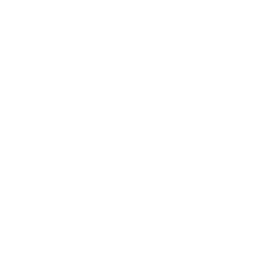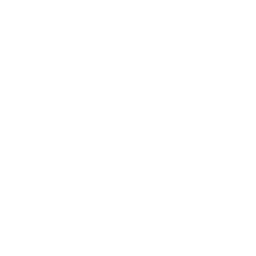硯の選び方❸〜硯の基礎知識⑥〜
硯の産地について
(1)日本の硯の産地〜その1〜
まず「日本三大硯」から紹介しよう。(グーグルから参考引用)
雄勝硯(おがつすずり):宮城県石巻市雄勝町で作られる硯で玄昌石(黒色硬質粘板岩)が使用される。黒色が美しく、鋒鋩(ほうぼう)が細かく均質で墨色が綺麗に出るのが特徴で、耐久性に優れ、長年の使用でも変化しにくいので硯に適している。
雨畑硯(あまはたすずり):山梨県早川町で作られる硯で雨畑石が使われる。石質は硬く、鋒鋩が立ち墨色も良い。硯の形や模様も美しく観賞用としても人気がある。
赤間硯(あかますずり):山口県宇部市で作られている硯で、石英や鉄分を多く含む緻密な石質が特徴。墨を細かく磨ることができ、古くから献上品として用いられ、伝統工芸品として親しまれている。
日本の硯で真っ先に押さえておきたいのは上記3点であるが、まだまだ魅力的な硯があるので北から順に見ていきたい。
1.紫雲石硯(しうんせきすずり):岩手県一関市で採れる紫雲石で作られる硯。小豆色や赤紫色の石に雲状の斑紋や緑色の円形斑点が入っているのが特徴で、鋒鋩は細かく墨色が良い。紫雲石は「正法寺石」とも言われ、東山町(現一関市)夏山、水沢市(現奥州市)正法寺付近で採掘され、古くは平泉・藤原三代の頃から生産された歴史を持っている。仙台藩公の「お止め山」の制度で一般の採掘は硬く禁じられていた。(いわての文化情報大事典HP参照)

2.雄勝硯:「日本三大硯」にも数えられている硯であるが、その歴史は古く約600年前の南北朝統一後の室町時代には生産が始まっていたと言われている。仙台藩祖伊達政宗が鹿狩りをするために牡鹿半島を訪れた際、硯を献上したところ非常に喜ばれ褒美を授かったとのこと。二代藩主忠宗はその技巧に感服し雄勝硯を作る硯師を藩お抱えとし、硯材を産出する山を「お止め山」として採石を制限した。江戸中期には雄勝硯は「雅物」として認知され名硯としてその名が広まったと考えられている。(雄勝硯生産販売協同組合HP参照)
1955年頃質の低い学童用硯の大量生産により雄勝硯のイメージは損なわれ、雄勝で作られたにもかかわらず雨畑硯の名前で販売したしたようだ。1985年(昭和60年)伝統的工芸品指定を受けたが2011年(平成23年)の東日本大震災による大津波で未曾有の被害を受け硯産地としても壊滅的な被害を被った。ボランティアの力や雄勝硯生産販売協同組合等の尽力により生産が再開されるとともに硯以外の商品の生産販売にも力を入れているようである。

3.大子硯(だいごすずり):茨城県大子町で産出される硯石で作られた硯。独特の黒いつや石紋は素朴で美しく「日本名硯」の一つに数えられ「国寿石大子硯」(こくじゅせきだいごすずり)とも言う。顕微鏡で見ると表面は星空のようにキラキラと輝いている。金を含んだ黄銅鉱で鋒鋩を作り出されている。大子町小久慈にある槐沢(さいかちざわ)は水戸藩2代藩主徳川光圀の時代から硯石の産地として知られ「御留山」(おとめやま)として保護。9代藩主斉昭らもこよなく愛し、国にとって吉兆であることを願い小久慈の音訓を取り「国寿硯」と命名した。昭和4年の茨城県で行われた陸軍特別大演習の際知事から昭和天皇に献上され翌年の東京での頒布会で著名人・文人・財界人からの注目を得た。(大子町振興公社HP参照)作家の武者小路実篤、政治家の犬飼毅らの著名人が愛用。
4.雨畑硯:ウィキペディアによると雨畑硯の起源は二つの説があり、一つは鎌倉時代の永仁5年(1297年)、日蓮の弟子日朗が七面山を開く際に早川支流の雨畑川で蒼黒色の石を発見し、この石で良質の硯が作れると伝えたのが始まりとする。もう一つは江戸時代前期の元禄3年(1690年)雨宮孫右衛門が身延山へ参詣した際早川で黒色の石を発見し、天明4年(1784年)に将軍徳川家治へ献上され名を高めたという説である。
雨畑硯の原石は特に希少な原石と産地を識別するために「雨畑真石」(あめはたしんせき)とも言われ、中国の端渓硯にも比肩しうる質感ときめ細かい肌触り、墨おりに優れていることから多くの文人に愛されてきた。緻密な粘板岩で粒子が細かく、水持ちが良く水分の吸収が少ないといった硯に最適な石材なのである。明治以降早くから有名になったことから別の地域の石が流入し「雨畑硯」の名前で販売されたことから「雨畑硯製造販売組合」が設立された。

5.龍渓硯(りゅうけいすずり):長野県辰野町の山中から産出される龍渓石が材料。石質は緻密で適度な硬さがあり、硯には最適。江戸時代後期漢学者渕井椿斎が硯を製作したのが起源で、その後高遠藩が財政難打開のためすべての硯石を所有し甲州から職人を招いて技術指導し硯作りをした。石の色は灰色で表面に微細な紋様がある。